本文
利用者負担額(保育料)のお知らせ

保育料は市民税所得割額を基準として算定します。
4月から8月分の保育料は前年度の市民税所得割額で、9月から翌年3月分の保育料は現年度の市民税所得割額で算定します。
父母の収入が少なく、同居している(世帯分離含む)祖父母が生計を支えていると認められる場合は、祖父母も算定対象となります。
保育料の算定方法
3歳以上児
幼児教育・保育無償化により3歳以上児の保育料は0円です。※保護者会費、副食費等は各園で別途徴収
3歳未満児
お子さんの父母の市民税所得割課税額を合算した額に応じて決定します(住宅借入金等特別控除、配当控除、寄付金控除など適用されないものもあります)。
なお、父母の収入が103万円未満の場合は、同居の祖父母等の課税額も含めて算定します。
山梨市では、保護者の負担を軽減するため、金額を国の基準より低く設定しています。
公立保育園も私立保育園等も保育料は同じです。
- 令和6年4月から令和6年8月までの利用者負担額(保育料)
→令和4年1月から令和4年12月までの収入から算出された令和5年度市民税の所得割額により算定 - 令和6年9月から令和7年3月までの利用者負担額(保育料)
→令和5年1月から令和5年12月までの収入から算出された令和6年度市民税の所得割額により算定
詳しくはR6利用者負担額(保育料)徴収金額表 [PDFファイル/169KB]のお知らせをご覧ください。
※令和6年9月1日現在の情報になります。利用者負担額(保育料)につきましては変更になることがあります。
保育料の変更
婚姻・離婚等により世帯構成が変更になった場合や、市民税の修正申告を行った場合は、保育料が変更となる場合があります。このような場合は、必ず「支給認定変更(延長)申請書兼記載内容変更届 [PDFファイル/242KB]」を提出してください。
【婚姻した場合】
保育料は、婚姻日の属する月の翌月から変更されます。婚姻する方の市民税所得割額を合算した保育料となります。また、同居人(内縁関係)がいる場合も、合算し算定します。
【離婚した場合】
変更届を提出した日の属する月の翌月から変更されます。(遡及はしませんので、速やかに変更届を提出してください。)離婚についての調停を裁判所に申し出た場合も相手方の分を除いて算定します。事件係属証明書が必要になりますので、変更届と合わせて提出してください。
ただし、離婚後も同居している場合は生計同一とみなし、保育料の変更はありません。
【修正申告した場合】
変更届を提出した日の属する月の翌月から変更されます。(遡及はしませんので、速やかに変更届を提出してください。)
保育料の減免
以下の場合において、保育料の軽減・減免制度が適用されます。
生活保護世帯
生活保護法による被保護世帯は免除されます。
※必要書類……生活保護を受給している証明
ひとり親世帯等の保育料負担軽減
ひとり親世帯、在宅障がい児(者)がいる世帯等に該当する場合で、市民税が非課税または市民税所得割額が一定未満の場合保育料が軽減されます。
【必要書類】
ひとり親世帯……児童扶養手当証書または戸籍謄本
在宅障がい児(者)がいる世帯……障害者手帳または特別児童扶養手当証書
| 収入制限 | 認定区分 | 対象となる世帯 | 軽減額 |
|---|---|---|---|
| 収入制限あり | 3号 | 利用者負担額(保育料)徴収金額表で第3~5階層の世帯 | 当該階層の保育料から1,000円を控除した額の半額。ただし、生計を一にする第1子の年齢にかかわらず第2子以降は無料 |
| 利用者負担額(保育料)徴収金額表で第6階層の世帯 | 9,000円とする。ただし、生計を一にする第1子の年齢にかかわらず第2子以降は無料 |
多子世帯の保育料負担軽減
多子世帯における保育料軽減は以下の通りです。
| 収入制限 | 認定区分 | 対象となる世帯 | 軽減額 |
|---|---|---|---|
| 収入制限なし | 3号 | 2人以上の児童が同時に保育園に入園している世帯 | 同時入園している最年長の子供から順に2人目は半額、3人目以降は無料 |
| 収入制限あり | 市民税の所得割額が57,700円未満の世帯 | 生計を一にする第1子の年齢にかかわらず、第2子は半額、第3子以降は無料 | |
| 市民税の所得割額が169,000円未満の世帯 |
※やまなし子育て応援事業 |
保育料の納入
保育園の場合
保育園の保育料は、口座振替によりお支払いいただきます。振替日は毎月25日です。(振替日が土曜日・日曜日、祝日の場合は、翌営業日となります。)
入園が決まりましたら「口座振替依頼書」に必要事項を記入のうえ、金融機関で手続きを行ってください。金融機関から市に「口座振替依頼書」が回送されるまでに時間がかかるため、早めの提出をお願いします。
振替日に引き落としができなかった場合には「納付書」を郵送します。必ず納期限までにお支払いください。
滞納した場合
納期限を過ぎても保育料を納入していただけない場合は、児童手当から徴収いたします。
一括納入が困難な場合は、納付相談により分割納入などでお支払いいただきます。それでも応じていただけない場合は、児童福祉法第56条で定める地方税法の滞納処分の例により、財産の差し押さえを行うことがあります。
認定こども園、幼稚園の場合
認定こども園、幼稚園の保育料は施設へ直接お支払いいただきます。支払方法は各施設により異なりますので、直接施設へお問い合わせください。
副食費について
無償化の対象となる3歳児クラス以上の給食費については、主食分は現物持参、副食分(おかず・おやつ)につきましては副食費を納入していただきます。副食費の料金、納入方法につきましては、各施設にご確認ください。
| 認定区分 | 対象となる世帯 |
|---|---|
| 1号 |
|
| 2号 |
|
保育料と同様に毎年9月が切り替え時期となります。副食費の免除対象者につきましては「副食費徴収免除のお知らせ」をお送りしますのでご確認ください。






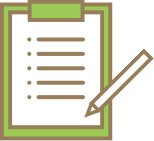 子育ての
子育ての 子育て
子育て イベント
イベント シティ
シティ